-
相 談 事 例
-
日常生活の中で、突然、お困りごとに直面する方が沢山います。誰に相談したらいいのか、どこに行けばいいのか、滅多にない事に慌ててしまう方も多いです。
簡易的なケーススタディーをご用意しました。解決の一助にお役立てくださいませ。
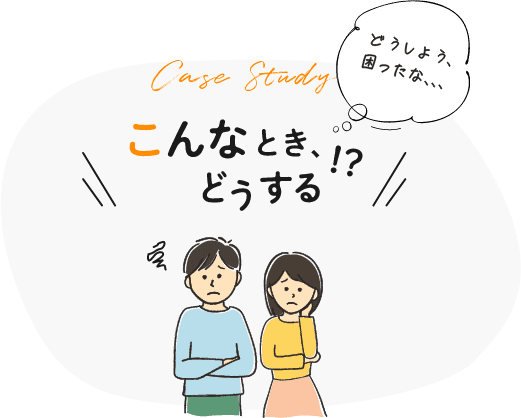
遺言
-
-
遺言とは何ですか?
-
遺言とは、ご自身の財産を誰にどのように承継させるか、またはその他の最終的な意思をご自身の死後に実現させるために、法律で定められた方式に従って作成する書面のことです。
遺言書を作成することで、ご自身の意思を明確にし、相続人間の紛争を未然に防ぐことができます。遺言には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など全部で7種類があります。
-
-
-
遺言書を作成するメリットは何ですか?
-
遺言書を作成する主なメリットは、
・ご自身の財産の承継先をご自身で指定できること
・相続人以外の第三者(お世話になった人や団体など)に財産を遺贈できること
・相続人間の遺産分割協議が不要になるため、相続手続きをスムーズに進められること
・相続人間の紛争を未然に防ぐことができること
などがあります。遺言書は、ご自身の意思を尊重し、相続を円滑に進めるための有効な手段となります。
-
-
-
遺言書にはどのような種類がありますか?またどのような違いがありますか?
-
遺言書には、主に以下の3種類があります。
・自筆証書遺言: 遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する遺言書です。手軽に作成できますが、方式の不備により無効になるリスクがあります。
・公正証書遺言: 遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が作成する遺言書です。公証人が内容を確認するため、最も確実な方法とされています。
・秘密証書遺言: 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、公証人にその存在を証明してもらう遺言書です。内容を秘密にできますが、自筆証書遺言と同様に方式の不備に注意が必要です。
-
-
-
自筆証書遺言を作成する際の注意点は何ですか?
-
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する必要があります。日付や氏名の記載がない場合、または自筆でない部分がある場合は、遺言が無効になる可能性があります。また、加除訂正の方法も法律で定められており、これに従わない場合も無効となることがあります。作成後には、相続人に遺言書の存在を伝え、保管場所を明確にしておくことが重要です。
-
-
-
公正証書遺言を作成するメリットは何ですか?
-
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、法的に有効な遺言書を作成するため、最も確実な方法とされています。原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。また、遺言者の判断能力に疑義がある場合でも、公証人が確認を行うため、遺言の有効性が争われるリスクを減らすことができます。
-
-
-
遺言書がない場合、相続はどうなりますか?
-
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であり、時間や労力がかかることがあります。
-
-
-
遺言書の内容は変更できますか?
-
はい、遺言書の内容は、遺言者が生存している限り、いつでも変更または撤回することができます。遺言書を書き直す、または撤回する旨を記載した遺言書を作成することで、以前の遺言書を無効にすることができます。常に最新の意思を反映した遺言書を作成することが重要です。
-
-
-
遺留分とは何ですか?
-
遺留分とは、法律で定められた相続人に保障される最低限の相続財産の割合のことです。兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)には遺留分が認められています。遺言書で特定の相続人の相続分を著しく少なくした場合でも、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を行うことができます。
-
-
-
遺言書の保管方法で注意することはありますか?
-
自筆証書遺言の場合、紛失や偽造を防ぐため、安全な場所に保管することが重要です。法務局における自筆証書遺言保管制度を利用することもできます。この制度を利用すると、法務局が遺言書を保管し、相続発生時に相続人に通知してくれます。公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配はありません。
-
-
-
遺言書の作成を専門家に依頼するメリットは何ですか?
-
遺言書の作成を司法書士などの専門家に依頼することで、法的に有効な遺言書を確実に作成できます。複雑な財産や相続関係がある場合でも、専門家が適切なアドバイスを行い、遺言者の意思を最大限に尊重した遺言書を作成してくれます。また、相続発生後の手続きについてもサポートを受けることができます。
-
相続
-
-
相続とは何ですか?
-
相続とは、人が亡くなった際に、その人が持っていた財産や権利、義務を、配偶者や子供などの親族が引き継ぐことをいいます。亡くなった方を「被相続人」、財産を受け継ぐ方を「相続人」といいます。相続は、民法という法律で定められたルールに基づいて行われます。遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されますが、遺留分という相続人に保障された最低限の相続割合もあります。
-
-
-
相続人になれる人は誰ですか?
-
相続人になれる人は、民法で定められた順位によって決まります。
・常に相続人となるのは、被相続人の配偶者です。配偶者以外の相続人は、順番が決められています。
・第1順位は、被相続人の子供です。子供が既に亡くなっている場合は、その子供の子供(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続)。
・第2順位は、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)です。子供や孫がいない場合に相続人となります。
・第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。子供、孫、直系尊属がいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供(被相続人の甥や姪)が相続人となります(代襲相続)。
-
-
-
遺産分割協議とは何ですか?
-
遺産分割協議とは、相続人全員で、遺産をどのように分けるかを話し合って決めることです。遺言書がない場合や、遺言書で全ての財産の分け方が指定されていない場合に、遺産分割協議を行います。相続人全員が合意すれば、自由に遺産の分け方を決めることができます。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
-
-
-
遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?
-
遺産分割協議が相続人同士の話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が相続人それぞれの意見を聞きながら、合意点を探ります。調停でも合意に至らない場合は、遺産分割審判に移行し、裁判官が遺産の分け方を決定します。
-
-
-
相続放棄とは何ですか?
-
相続放棄とは、相続人が、被相続人の財産を一切相続しないという意思表示をすることです。相続放棄をすると、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎません。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
-
-
-
限定承認とは何ですか?
-
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済するという条件で相続することです。相続財産の中にプラスの財産とマイナスの財産がある場合、限定承認をすることで、相続人が自分の財産で被相続人の借金を支払う必要がなくなります。限定承認は、相続人全員で共同して行う必要があり、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
-
-
-
遺留分とは何ですか?
-
遺留分とは、法律で定められた相続人に保障される最低限の相続財産の割合のことです。兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)には遺留分が認められています。遺言書で特定の相続人の相続分を著しく少なくした場合でも、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
-
-
-
遺産の中に不動産がある場合、どのように相続手続きを進めますか?
-
遺産の中に不動産がある場合、法務局で相続登記(不動産の名義変更)を行う必要があります。相続登記には、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書(または遺言書)、不動産の登記簿謄本などの書類が必要です。司法書士に依頼することで、煩雑な書類作成や手続きを代行してもらうことができます。
-
-
-
相続税はどのような場合に発生しますか?
-
相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に発生します。基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。相続税の申告と納税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
-
-
-
相続に関する相談はどこにすれば良いですか?
-
相続に関する相談は、司法書士、弁護士、税理士などの専門家にすることができます。司法書士は、相続登記や遺言書作成などをサポートします。また遺産承継業務として遺産の相続手続全般のサポートを行ったり、死後の様々な手続き(葬儀や永代供養、遺品整理や各種届出など)をサポートすることもできます。
-
相続登記義務化
-
-
相続登記の義務化とは何ですか?
-
相続登記の義務化とは、相続によって不動産を取得した相続人が、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないとする制度です。2024年4月1日から施行されました。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
-
-
-
なぜ相続登記が義務化されたのですか?
-
相続登記の義務化の主な目的は、所有者不明土地の発生を抑制することです。相続登記がされないまま放置された土地は、所有者が分からなくなり、公共事業や災害復旧の妨げになることがあります。義務化によって、不動産の所有者情報を明確にし、土地の有効活用を促進することが期待されています。
-
-
-
相続登記の申請期間はいつから起算されますか?
-
相続登記の申請期間は、相続人が不動産の所有権を取得したことを知った日から起算して3年以内です。例えば、遺産分割協議が成立した日や、遺言書の内容を知った日が起算日となります。
-
-
-
相続登記をしなかった場合、どのようなペナルティがありますか?
-
正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、単に期限を過ぎただけで直ちに過料が科されるわけではなく、法務局から登記申請の催告を受け、それでも対応しない場合に過料が科されることがあります。
-
-
-
相続登記にはどのような書類が必要ですか?
-
相続登記に必要な書類は、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書(または遺言書)、不動産の登記事項証明書、相続人の住民票などです。場合によっては、固定資産評価証明書や印鑑証明書なども必要になります。司法書士に依頼することで、必要な書類の収集や作成を代行してもらうことができます。
-
-
-
遺産の中に未登記の不動産がある場合はどうすれば良いですか?
-
遺産の中に未登記の不動産がある場合でも、相続登記の義務は発生します。まずは、専門家(司法書士など)に相談し、未登記の原因や経緯を調査する必要があります。その上で、登記に必要な書類を収集し、表題登記と所有権保存登記を同時に申請する必要があります。
-
-
-
相続登記の費用はどのくらいかかりますか?
-
相続登記の費用は、登記をする際に必要な登録免許税、書類取得費用、司法書士への報酬などで構成されます。登録免許税は、不動産の固定資産評価額に一定の税率(相続を原因とする場合には0.4%)をかけた金額になります。司法書士への報酬は、不動産の数や評価額、相続人の数などによって異なります。
-
-
-
相続登記を自分で行うことはできますか?
-
相続登記は、ご自身で行うことも可能です。しかし、必要な書類の収集や作成、法務局での手続きなど、専門的な知識が必要となる場面も多くあります。司法書士に依頼することで、時間や手間を省き、確実な手続きを行うことができます。
-
-
-
相続登記の義務化に関する相談はどこにすれば良いですか?
-
相続登記の義務化に関する相談は、司法書士、弁護士などの専門家にすることができます。司法書士は、相続登記の専門家ですので、複雑な相続手続きもサポートできます。また、法務局でも、一般的な相談を受け付けています。
-
相続法改正
-
-
いつから変わったの?
-
①自筆証書遺言の方式を緩和する方策について … 平成31年1月13日から
②預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、特別の寄与等(①③④以外の規定)…令和元年7月1日から
③配偶者保護のための方策(配偶者短期居住権・配偶者居住権の新設)…令和2年4月1日から
④法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設…令和2年7月10日から
-
-
-
どんな改正か簡単に教えて
-
高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応するための改正です。
・自筆証書遺言を作成するときに、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。
・遺産分割の前でも亡くなられた方の預貯金を一部払い戻すことができるようになりました。
・亡くなられた方の親族で療養看護等を行った方は、相続人に対し、その貢献に応じた金銭を請求することができるようになりました。
・亡くなられた方の配偶者がそれまで住んでいた建物に住み続けられやすくするための方策が新設されました。
-
-
-
法務局における自筆証書遺言の保管制度とは?
-
改正前は、せっかく遺言書を自筆で作っても、保管した場所が家族に伝わらずに遺言書を見つけてもらえない場合がありました。また、相続人がこっそり遺言書を捨ててしまったり、内容を改ざんしてしまうことも考えられました。今回の改正で、遺言書を法務局が保管してくれる制度が創設され、遺言書の紛失や隠匿、改ざん等を防止することができるようになりました。また、これまで必要であった家庭裁判所における「検認手続」も不要になりました。この改正は、令和2年7月10日から施行されました。
-
-
-
遺産分割前の預貯金の払戻し制度とは?
-
改正前は、亡くなられた方(被相続人)の葬儀費用や未払い入院費を支払うために、一部の相続人から被相続人の預貯金の払い戻しを請求することはできませんでした。今回の改正では、相続人のこのような資金需要に対応できるように、各相続人が単独で被相続人の預貯金のうち一定割合の払戻しを受けられるようになりました。払い戻しを受けることができる具体的な金額は、相続時の預貯金残高×3分の1×相続人の法定相続割合です。ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までです。この制度は被相続人が令和元年7月1日より前に亡くなっていた場合でも利用できます。
-
-
-
配偶者短期居住権とは?
-
相続開始後も配偶者が被相続人の建物に無償で居住できたのは、従来、被相続人がそれを認めていたと推認できる場合だけでした。被相続人がその建物を第三者に遺贈したり、被相続人が配偶者の居住を認めない意思を表示した場合には、配偶者はその建物に無償で居住できなかったのです。今回の改正で、相続開始時に配偶者が被相続人の建物に無償で住んでいた場合には、被相続人の意思にかかわらず、配偶者が一定期間(最低6か月間)その建物に無償で居住できることとなりました。これを「配偶者短期居住権」といいます。この改正は、令和2年4月1日から施行されました。
-
-
-
配偶者居住権とは?
-
相続開始後も配偶者が被相続人の建物に終身居住するためには、従来、被相続人の遺贈や遺産分割により、配偶者がその建物の「所有権」を取得するのが一般的でした。ただし、その建物の評価額が高い場合、配偶者はそれ以外の預貯金等の財産の相続は法定相続分を超えることもあり、相続ができない場合もありました。今回の改正で「所有権」よりも評価額の低い「配偶者居住権」が創設されたことにより、配偶者は「配偶者居住権」を取得することにより被相続人の建物に無償で終身居住しながら、それ以外の預貯金等の財産も相続できるようになりました。この改正は、令和2年4月1日から施行されました。
-
-
-
遺留分制度の改正点は?
-
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された一定割合の相続財産です。改正により「遺留分侵害額請求」に名称が変わりました。改正前は、遺留分減殺請求がされると、遺留分減殺請求の対象となる財産の種類を問わず、当然に被請求者と請求者とで共有関係が生じ、その共有関係を解消するため最終的には金銭によって解決が図られていました。今回の改正で、遺留分を請求しても共有にはならず、直ちに金銭の請求ができるものと改められました。
-
-
-
法定相続分を超えて相続した場合、相続登記は必要ですか?
-
改正前は、例えば遺言により法定相続分を超えて被相続人の不動産を相続することとなった場合でも、相続人は第三者に対して当然に法定相続分以上の権利を主張することができました。今回の改正では、相続人がこれを第三者に主張するには登記が必要となりました。法定相続分を超えて不動産を相続した相続人は、被相続人の死後、速やかに相続登記をする必要があります。
-
-
-
自筆証書遺言の改正点は?
-
自筆証書遺言とは、遺言者が手書きで作成した遺言です。改正前は、遺言者がその全文を手書きする必要がありました。今回の改正で、遺言の目的となる財産を示した「財産目録」の部分はパソコンで作成することも可能となりました。また、財産目録として通帳のコピーを添付することも可能です。ただし、財産目録の各頁に署名押印が必要となりますのでご注意ください。
-
-
-
相続人以外の者の貢献を考慮する制度とは?
-
改正前は、被相続人の長男の妻が被相続人の療養看護に無償で努めたとしても、長男の妻は相続人ではないので何も遺産をもらうことはできませんでした。今回の改正で、相続人以外の親族が被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合(「特別寄与者」と言います。)は、相続人に対して特別寄与料の請求ができるようになりました。特別寄与料の請求は相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、または相続開始の時から1年以内と期限があるので、まずはお近くの司法書士にご相談ください。
-
不動産登記
-
-
不動産登記とは何ですか?
-
不動産登記とは、土地や建物などの不動産に関する権利関係を、法務局に登記することです。不動産登記をすることで、所有権や抵当権などの権利を保全し、第三者に対抗することができます。不動産取引においては、登記された情報が重要な役割を果たします。
-
-
-
不動産登記が必要な場合はどのようなときですか?
-
不動産登記が必要となる主な場合は以下の通りです。
・不動産の購入
・不動産の贈与
・不動産の相続
・住宅ローンの設定
・登記した住所や氏名の変更
・建物の新築・増築
-
-
-
不動産登記はどこで行いますか?
-
不動産登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。オンラインによる登記申請も可能です。
-
-
-
不動産登記の申請は自分で行うことができますか?
-
不動産登記は、ご自身で行うことも可能です。しかし、必要な書類の収集や作成、法務局での手続きなど、専門的な知識が必要となる場面も多くあります。司法書士に依頼することで、時間や手間を省き、確実な手続きを行うことができます。
-
-
-
不動産登記に必要な書類は何ですか?
-
不動産登記に必要な書類は、登記の種類によって異なります。一般的に必要な書類としては、登記申請書、登記原因証明情報(売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書など)、不動産の登記識別情報または登記済証、印鑑証明書、住民票などがあります。法務局のホームページでは、各種登記の申請書様式をダウンロードすることができます。(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html)
-
-
-
不動産登記の費用はどのくらいかかりますか?
-
不動産登記の費用は、登録免許税、書類取得費用、法書士への報酬などで構成されます。登録免許税は、不動産の評価額に一定の税率をかけた金額になります。司法書士への報酬は、内容や手続きの複雑さなどによって異なります。
-
-
-
住所や氏名が変わった場合、不動産登記も変更する必要がありますか?
-
住所や氏名が変わった場合、不動産登記の変更登記をする必要があります。これは、登記されている情報と現在の情報を一致させるために重要です。変更登記をすることで、将来的な不動産取引や相続手続きをスムーズに進めることができます。
-
-
-
相続した不動産を放置するとどうなりますか?
-
相続した不動産を放置すると、将来的に売却や活用が困難になる場合があります。また、固定資産税がかかり続けるだけでなく、管理責任も発生します。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、3年以内に登記をしないと過料が科される可能性もあります。
-
-
-
抵当権設定登記とは何ですか?
-
抵当権設定登記とは、住宅ローンなどを利用する際に、不動産に抵当権を設定する登記です。抵当権を設定することで、債権者(金融機関など)は、債務者が返済できなくなった場合に、不動産を売却して債権を回収することができます。
-
-
-
不動産登記に関する相談はどこにすれば良いですか?
-
不動産登記に関する相談は、司法書士、弁護士などの専門家にすることができます。司法書士は、不動産登記の手続きの専門家ですので、複雑な登記手続きもサポートできます。また、法務局でも、一般的な相談を受け付けています。をサポートします。
-
商業登記
-
-
商業登記とは何ですか?
-
商業登記とは、会社や法人の設立、役員の変更、本店移転などの重要な事項を、法務局に登記することです。商業登記は、会社法や一般社団法人及び一般財団法人法などの法律に基づいて行われます。商業登記をすることで、会社や法人の情報を公開し、取引の安全を図ることができます。
-
-
-
商業登記が必要な場合はどのようなときですか?
-
商業登記が必要となる主な場合は以下の通りです。
・会社・法人の設立
・役員(取締役、監査役など)の変更
・本店・支店の移転
・会社の商号・目的の変更
・資本金の額の変更
・合併・会社分割
・解散・清算
-
-
-
商業登記はどこで行いますか?
-
商業登記は、会社・法人の本店所在地を管轄する法務局で行います。法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。オンラインによる登記申請も可能です。
-
-
-
商業登記の申請は自分で行うことができますか?
-
商業登記は、ご自身で行うことも可能です。しかし、必要な書類の作成や法務局での手続きなど、専門的な知識が必要となる場面も多くあります。司法書士に依頼することで、時間や手間を省き、確実な手続きを行うことができます。
-
-
-
商業登記に必要な書類は何ですか?
-
商業登記に必要な書類は、登記の種類によって異なります。一般的に必要な書類としては、登記申請書、議事録、定款、印鑑証明書などがあります。法務局のホームページでは、各種登記の申請書様式をダウンロードすることができます。
-
-
-
商業登記の費用はどのくらいかかりますか?
-
商業登記の費用は、登録免許税、書類取得費用、司法書士への報酬などで構成されます。登録免許税は、登記の種類や資本金の額などによって異なります。司法書士への報酬は、手続きの内容や複雑さなどによって異なります。
-
-
-
商業登記を放置するとどうなりますか?
-
商業登記を放置すると、会社法違反となる場合があります。また、代表者の住所変更登記を怠ると、職権で登記が抹消されることがあります。さらに、休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われ、解散したものとみなされることがあります。
-
-
-
代表取締役の住所を非表示にすることはできますか?
-
商業登記規則等が改正され、代表取締役等の住所を非表示にする措置が創設されました。この措置を利用することで、プライバシー保護を図ることができます。
-
-
-
商業登記に関する相談はどこにすれば良いですか?
-
商業登記に関する相談は、司法書士、弁護士などの専門家にすることができます。司法書士は、商業登記の専門家ですので、複雑な相続手続きもサポートできます。また、法務局でも、一般的な相談を受け付けています。
-
多重債務問題
-
-
特定調停とは何ですか
-
簡易裁判所に調停の申立てを行い、調停委員会の調整により、債権者との間で借金の返済について合意する手続きです。特定調停で合意し作成された調停調書は、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。
-
-
-
個人民事再生とは何ですか
-
地方裁判所に民事再生の申立てを行い、法律の定めに従って原則3年間の分割返済計画を作成します(例外5年間)。裁判所がその返済計画を認可した場合、元本の一部がカットされ、残りを分割で返済するという手続きです。
-
-
-
消費者金融から払い過ぎた利息を取り戻せるって本当ですか?
-
利息制限法で利息の上限が定められ、それを超える利息の契約は無効と定められています。
このため、取引履歴を取り寄せ法律で定められた利率で計算し直し、払いすぎた利息を取り戻すことができます。
-
-
-
自己破産すると自動車を手放さなければいけませんか。
-
自動車を担保としてローンを締結している場合や査定額が一定額以上の場合は自動車を手放す必要があります。
ただし、自由財産の拡張制度があり、破産者の経済生活の再生の機会の確保のため、保有が認められる場合もありますので、お近くの司法書士にご相談ください。
-
-
-
任意整理とはなんですか。
-
司法書士が、お金を貸してくれた方(債権者)と直接交渉し、支払金額・支払回数・支払方法など分割返済について債権者と和解して解決する手続きです。司法書士が代理できる範囲は、1社につき140万円(元金のみ)以内です。
-
成年後見
-
-
成年後見制度とは何ですか?
-
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法的に保護・支援する制度です。この制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見制度は、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、ご本人の財産管理や身上監護を行う制度です。任意後見制度は、ご本人が将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ信頼できる方と任意後見契約を結んでおく制度です。
-
-
-
法定後見制度にはどのような種類がありますか?
-
法定後見制度には、後見、保佐、補助の3種類があります。判断能力の程度に応じて、家庭裁判所が適切な類型を選択します。
後見は、判断能力がほとんどない方を対象とし、成年後見人が包括的な支援を行います。保佐は、判断能力が著しく不十分な方を対象とし、保佐人が特定の法律行為について同意権や取消権を持ちます。補助は、判断能力が不十分な方を対象とし、補助人が特定の法律行為について同意権、取消権または代理権を持つことがあります。
-
-
-
任意後見制度とはどのような制度ですか?
-
任意後見制度は、ご本人が将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ信頼できる方と任意後見契約を結んでおく制度です。ご本人が契約内容を決定できるため、ご本人の意思を尊重した支援が可能になります。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって締結する必要があります。任意後見監督人が選任されることで、任意後見人の業務が適切に行われているかチェックされます。
-
-
-
成年後見人には誰がなれますか?
-
成年後見人には、親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門家などがなることができます。家庭裁判所が、ご本人の状況や希望、成年後見人候補者の適格性などを考慮して選任します。成年後見人は、ご本人の財産を管理し、身上監護を行う上で、ご本人の意思を尊重し、ご本人の福祉に配慮する義務があります。
-
-
-
成年後見制度を利用するにはどうすればよいですか?
-
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立てができるのは、ご本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などです。申立ての際には、ご本人の戸籍謄本、診断書、財産に関する資料などを提出する必要があります。家庭裁判所は、これらの資料に基づいて審理を行い、成年後見人等を選任します。
-
-
-
未成年後見制度とは何ですか?
-
未成年後見制度は、親権者がいない、または親権を行えない未成年者を保護・支援する制度です。親権者が死亡したり、親権喪失の宣告を受けたりした場合に、家庭裁判所が未成年後見人を選任します。未成年後見人は、未成年者の財産管理や身上監護を行い、未成年者の成長をサポートします。
-
-
-
成年後見制度と未成年後見制度の違いは何ですか?
-
成年後見制度は、判断能力が不十分な成人を対象とする制度であるのに対し、未成年後見制度は、親権者がいない、または親権を行えない未成年者を対象とする制度です。成年後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型がありますが、未成年後見制度には類型区分はありません。
-
-
-
成年後見制度を利用する際の注意点はありますか?
-
成年後見制度を利用する際には、成年後見人等に対する報酬が発生場合があること、成年後見人等による財産管理が制約を受けること、ご本人の自己決定権が制限される可能性があることなどに注意が必要です。制度利用前に、専門家や相談窓口に相談し、制度のメリット・デメリットを十分に理解することが重要です。
-
裁判
-
-
よくわからないが、いきなり裁判所から訴状が届いた!
-
無視してはいけません。あなた(被告)に対する訴訟の呼出状であれば,定められた期日に裁判所へ出頭せず,答弁書(被告の言い分を書いた書面)も提出しないと,仮に原告の請求が退けられるものであったとしても,欠席判決で原告の請求がそのまま認められてしまうかもしれません。
-
-
-
友人が貸したお金を返してくれません。
-
何もしないでいると消滅時効を援用されお金を返してもらえなくなります。返してほしいと請求しているだけでは足りません。まずは内容証明郵便で相手方に返してほしいと催告(通知)をする事が重要です。催告後6ヶ月以内に裁判をするか、相手方に借金の返済を約束させることで時効が中断します。
-
-
-
大家さんが敷金を返してくれず困っています。
-
賃貸借契約が終了した場合、借主は賃借物を原状(元の状態)に戻して貸主に返さなければいけません。これを原状回復義務といいます。もっとも、普通に生活をしていても劣化していきますので、借主は通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損についてのみ修繕する必要があります。従って、貸主は、原則、敷金から通常損耗の費用を精算することはできません。
通常の使用を超えるような損耗や毀損があったのか、契約時に原状回復に関する特約についてどのような説明を受けていたかを確認し、まずは司法書士へご相談ください。
-
労働問題
-
-
パートタイムでも有休は取得できるのでしょうか
-
パートタイムであっても、雇い入れの日から6か月間継続して勤務しており、全労働日の8割以上出勤していること、という条件を満たしていれば有給休暇を取得することが認められています。なお、前労働日の8割以上の出勤とは、雇用契約で定められた労働日の8割以上という意味です。
-
-
-
採用が決まったのにギリギリになって内定取り消しされました。
-
内定とは、その時点で労働契約が成立している状態をいいます。よって、不当な内定取り消しは解雇に相当し、違法となる可能性があります。ただし、内定を取り消されてもやむを得ない理由がある場合は、認められることもあります。
-
-
-
突然、明日からもう来なくていいと言われました。
-
解雇する意味での言葉であれば、例えば客観的にみて解雇もやむを得ない合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合でなければなりません。また、会社がやむを得ず解雇する場合には、”解雇予告の手続き”が必要となります。法律上、会社は退職する30日以上前に解雇予告をしなければなりません。即日解雇する場合には、平均賃金の30日分以上に相当する解雇予告手当を支払わなければなりません。
-




